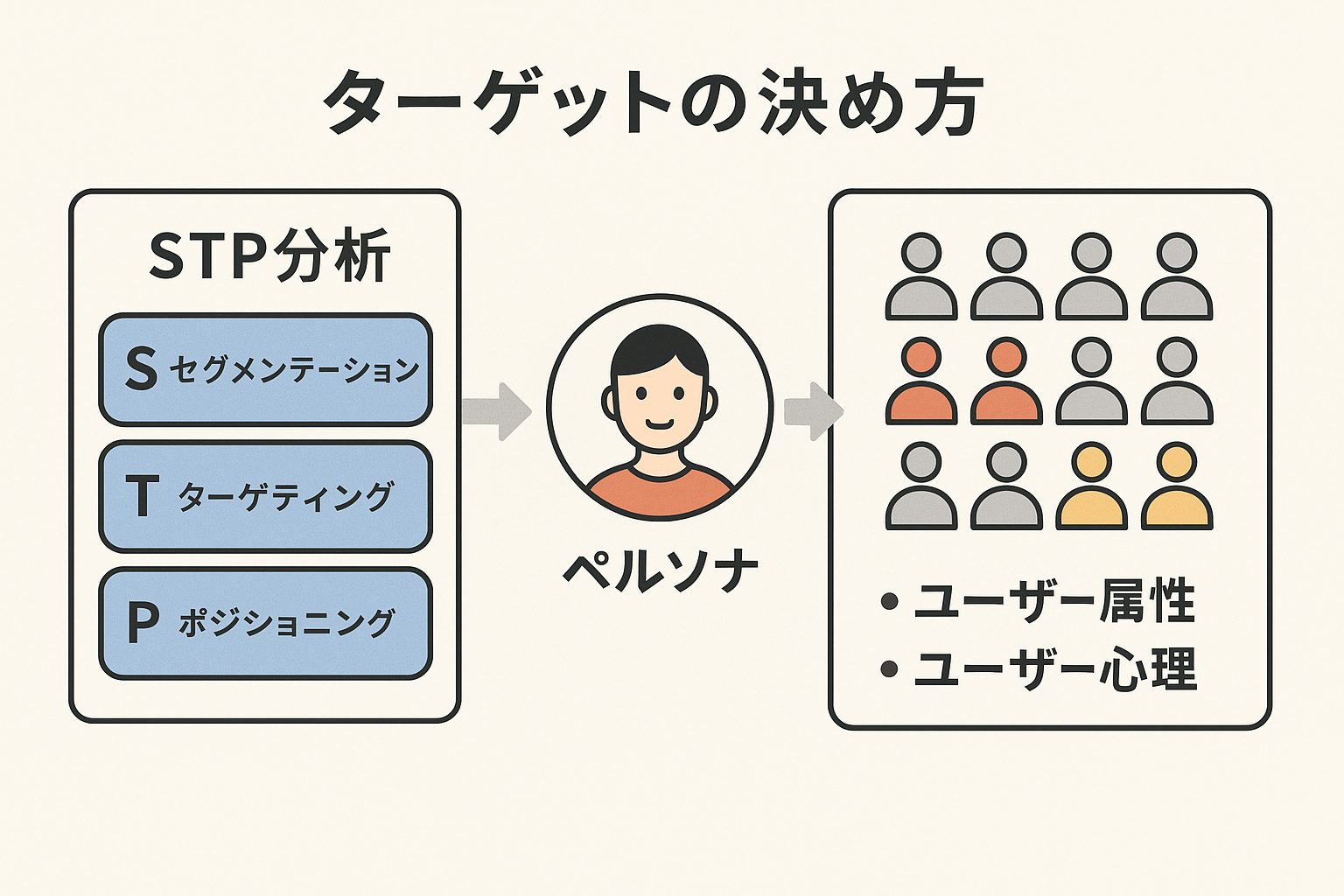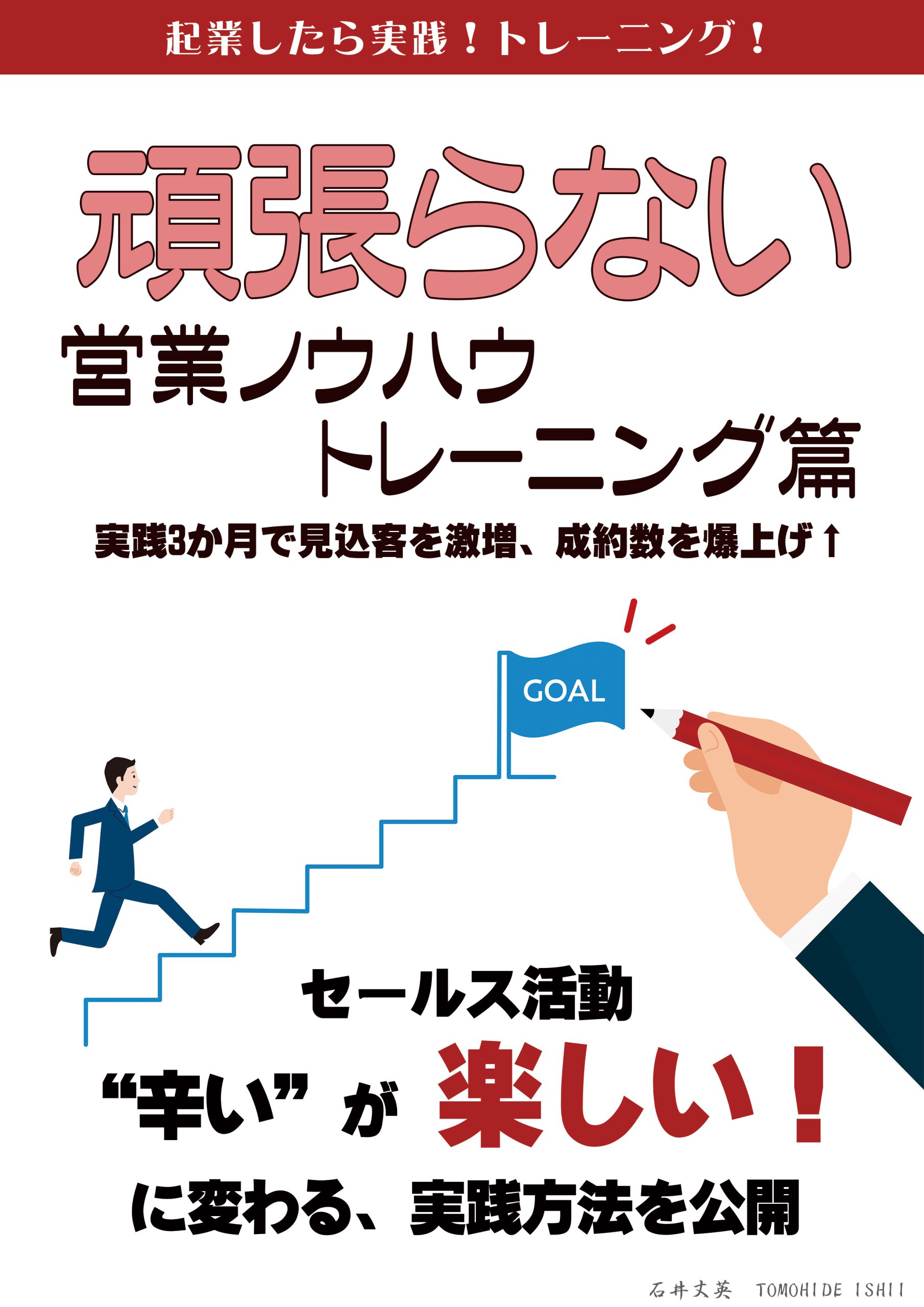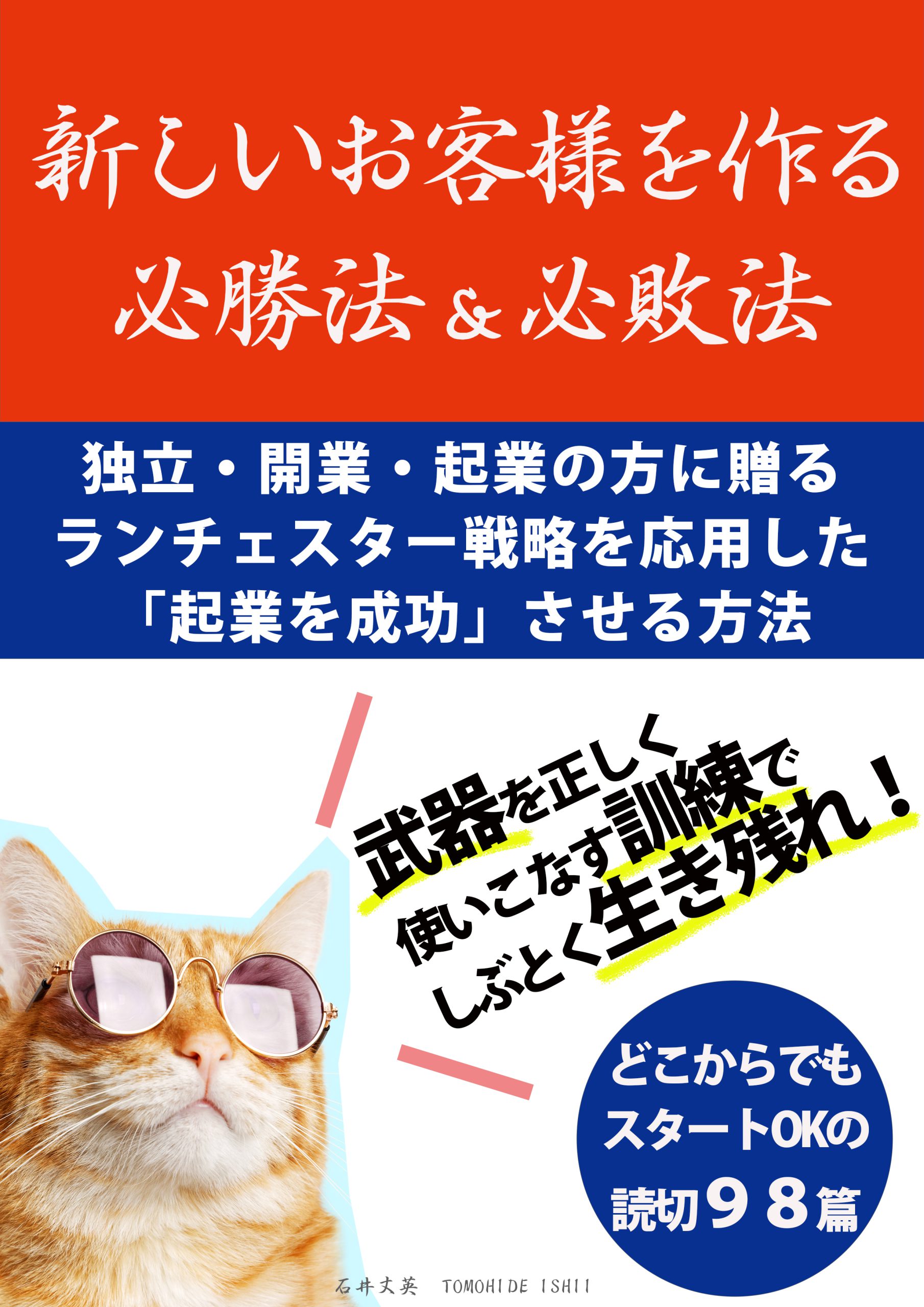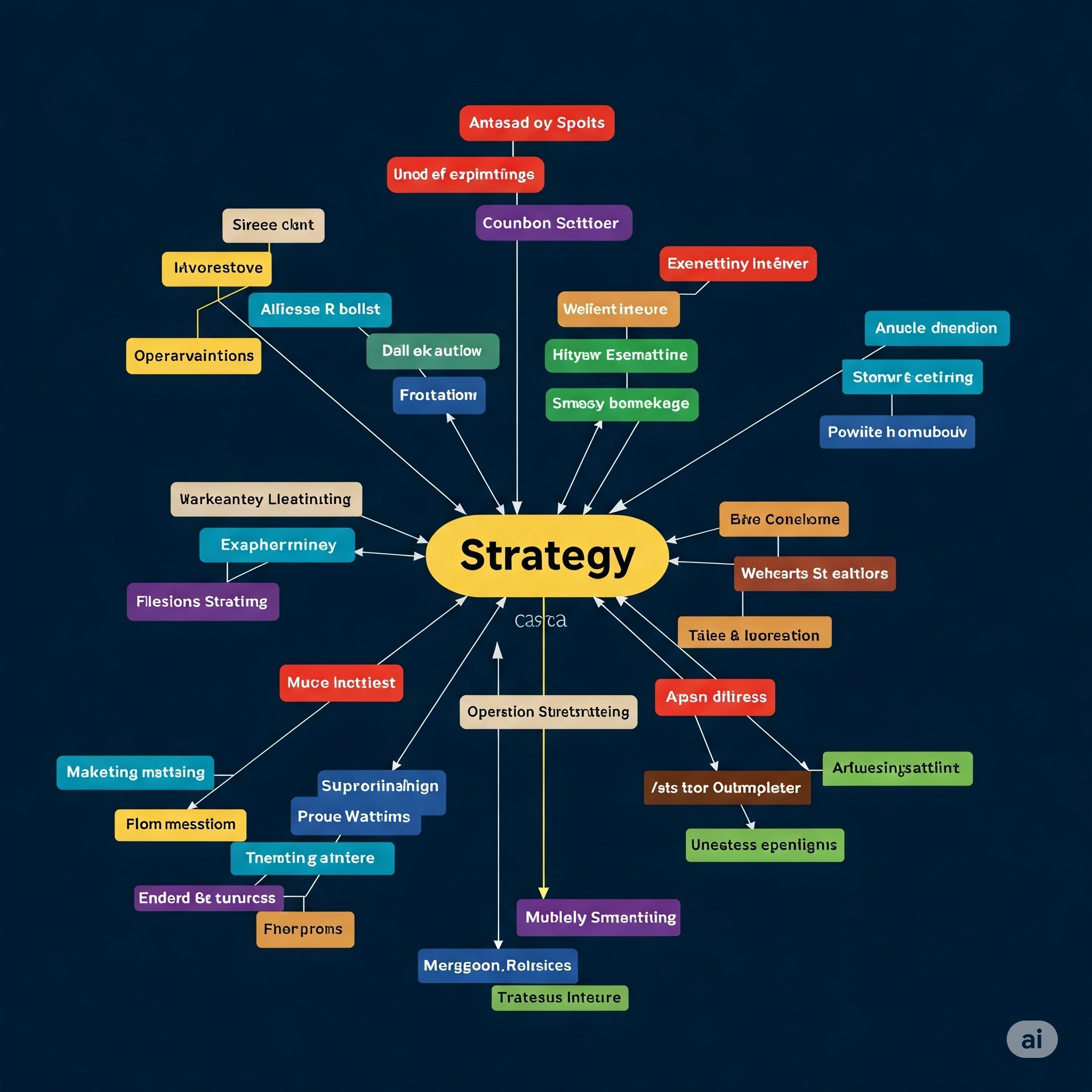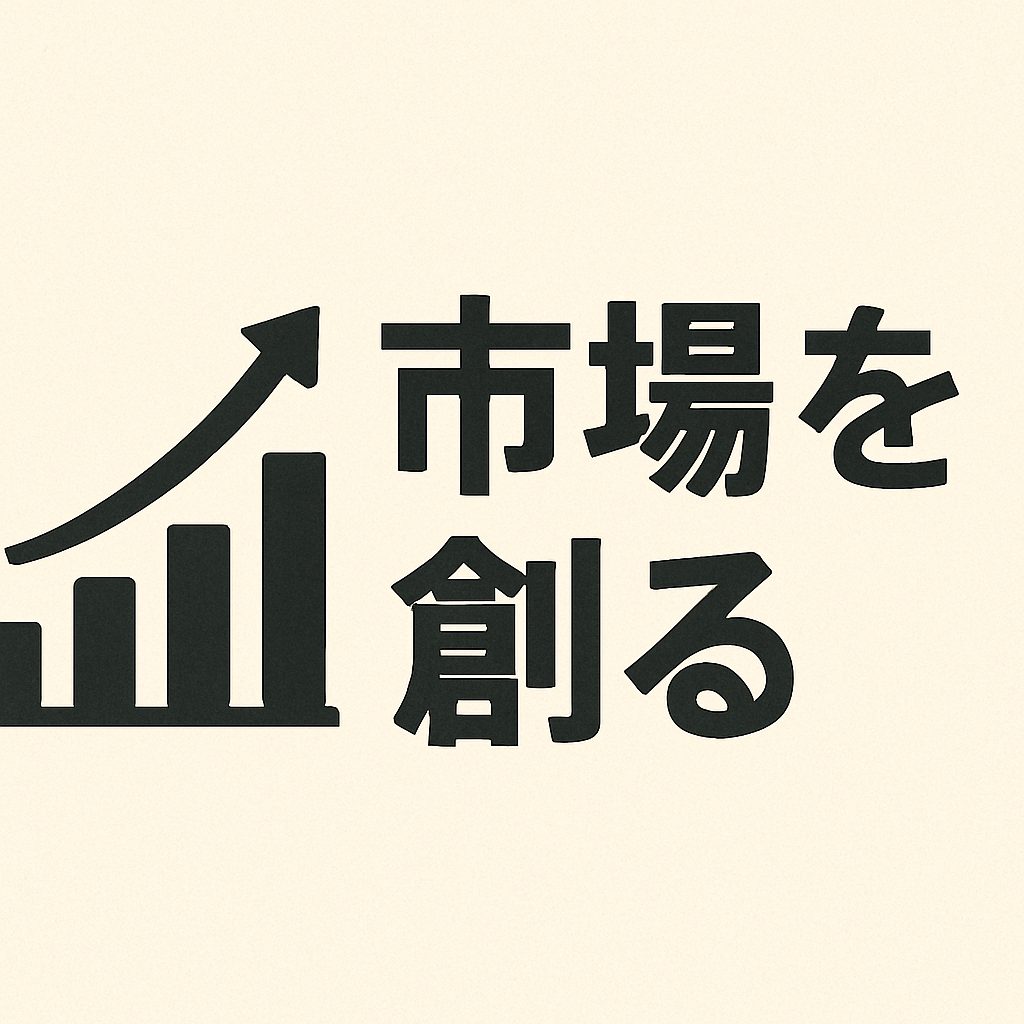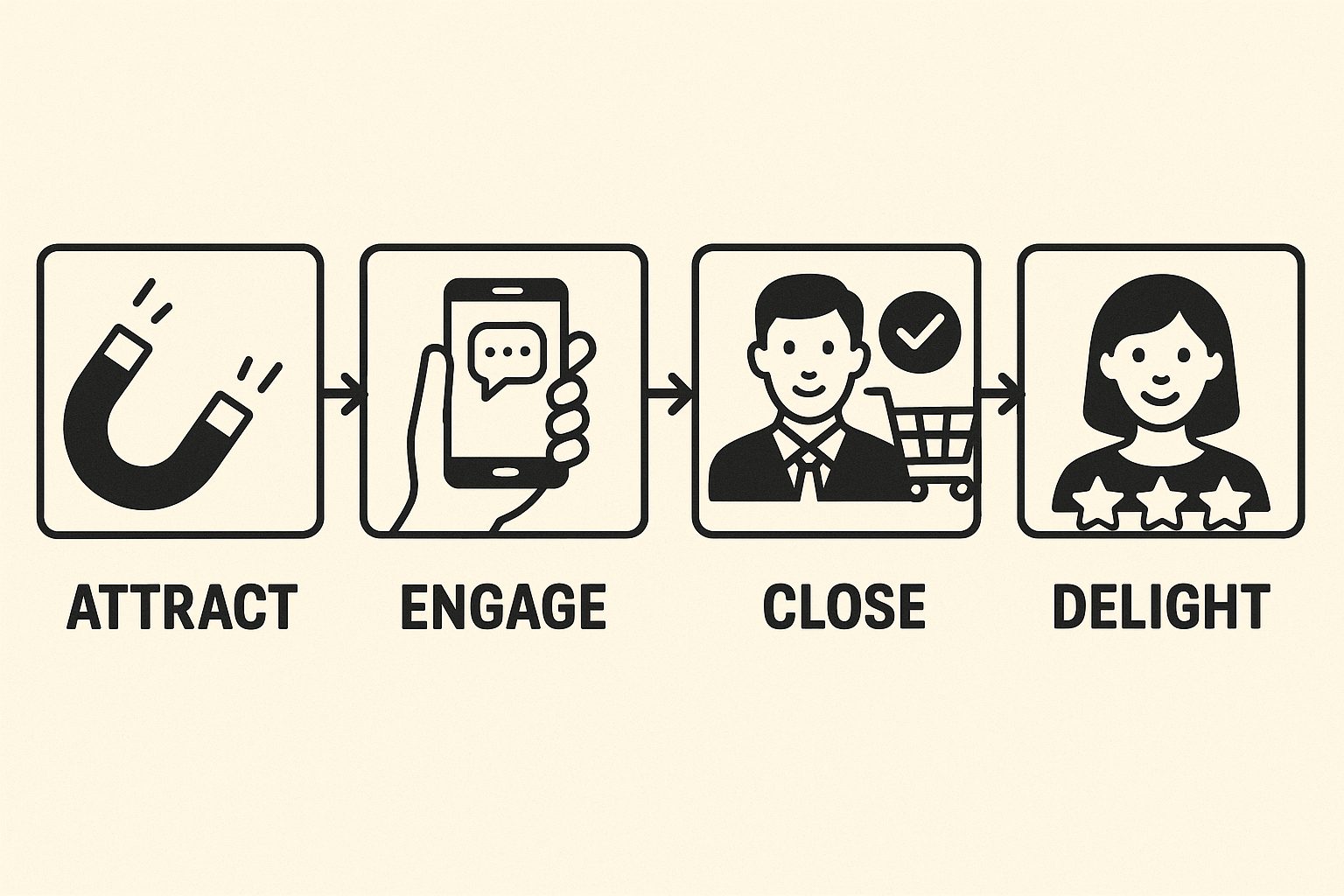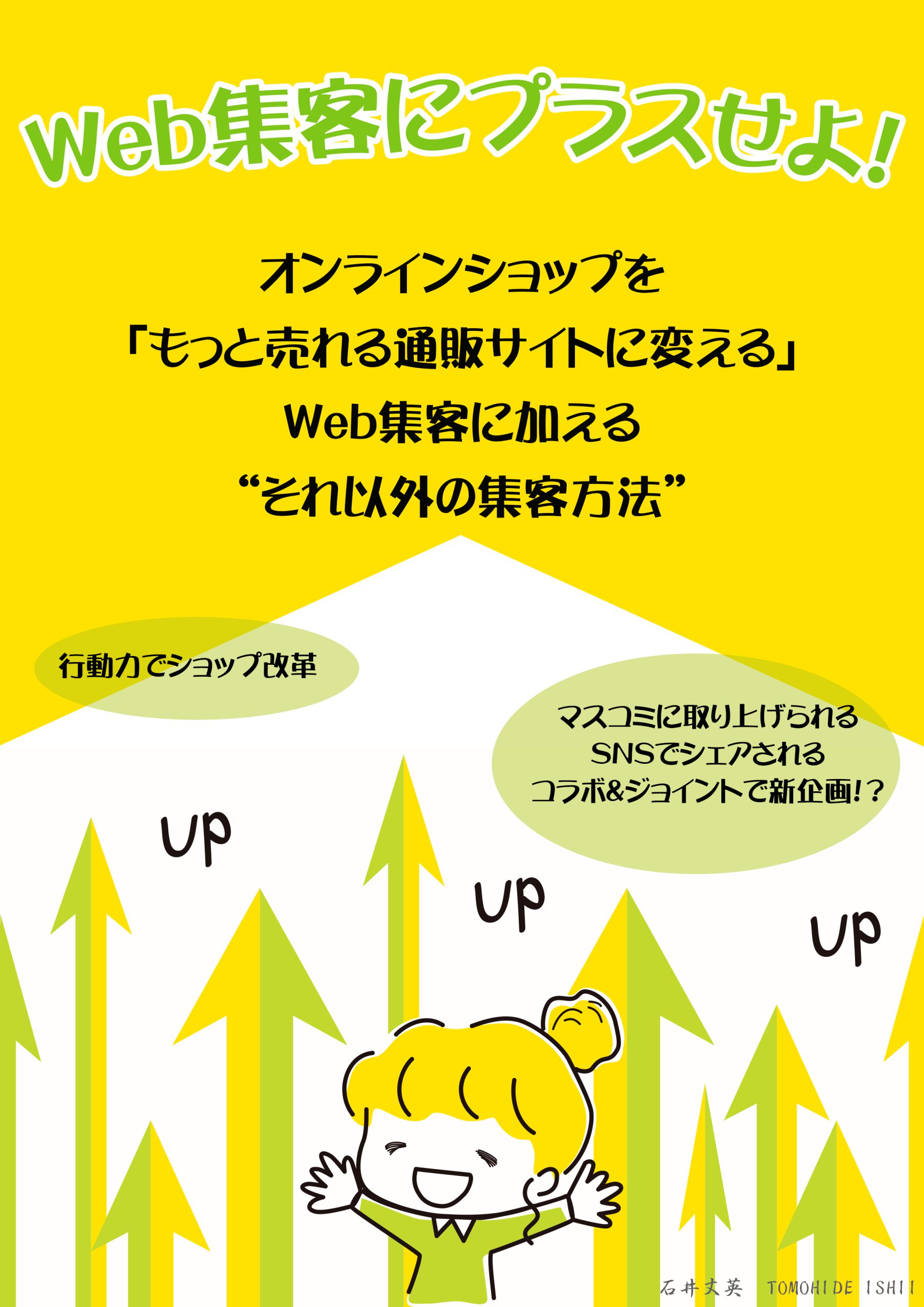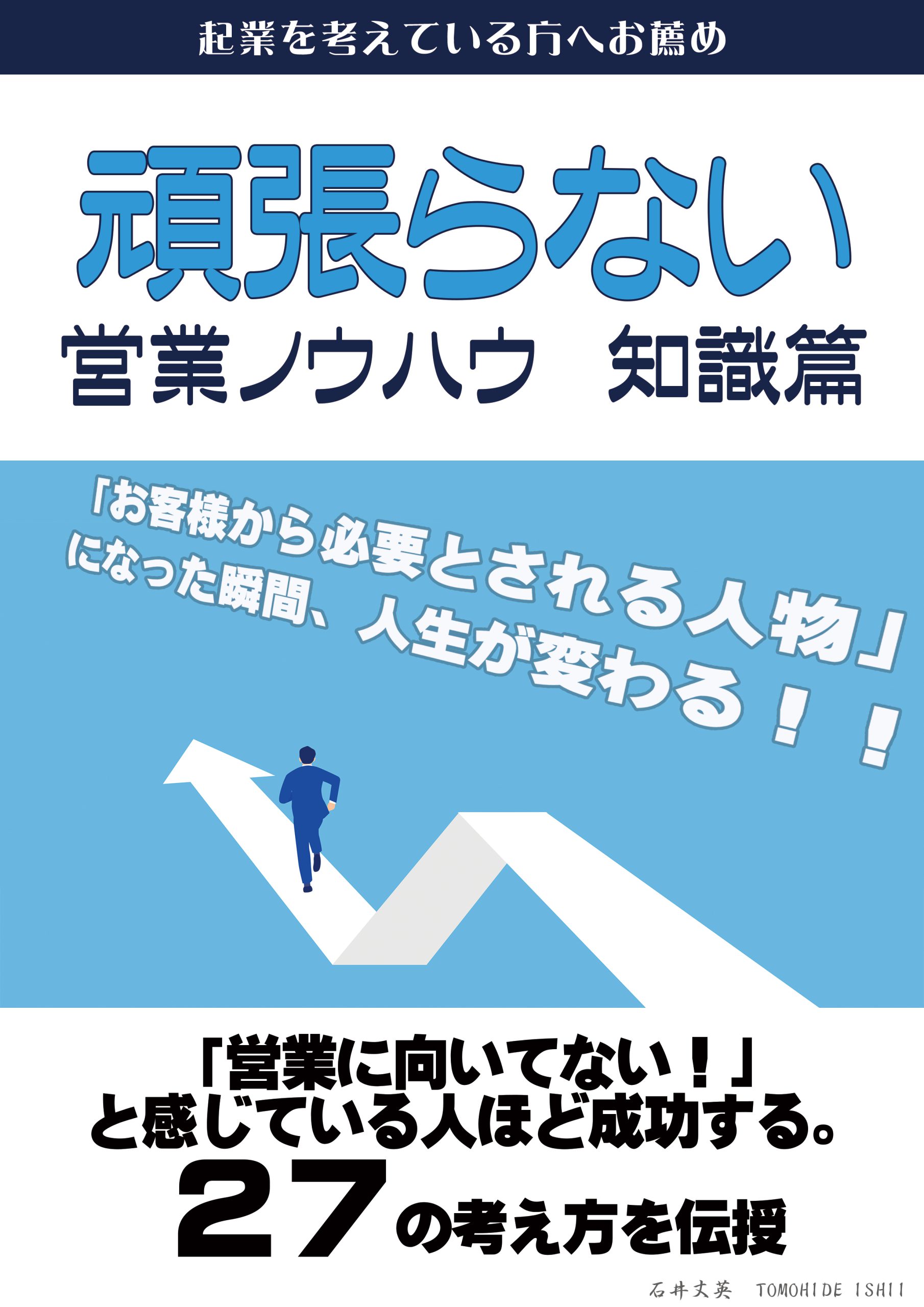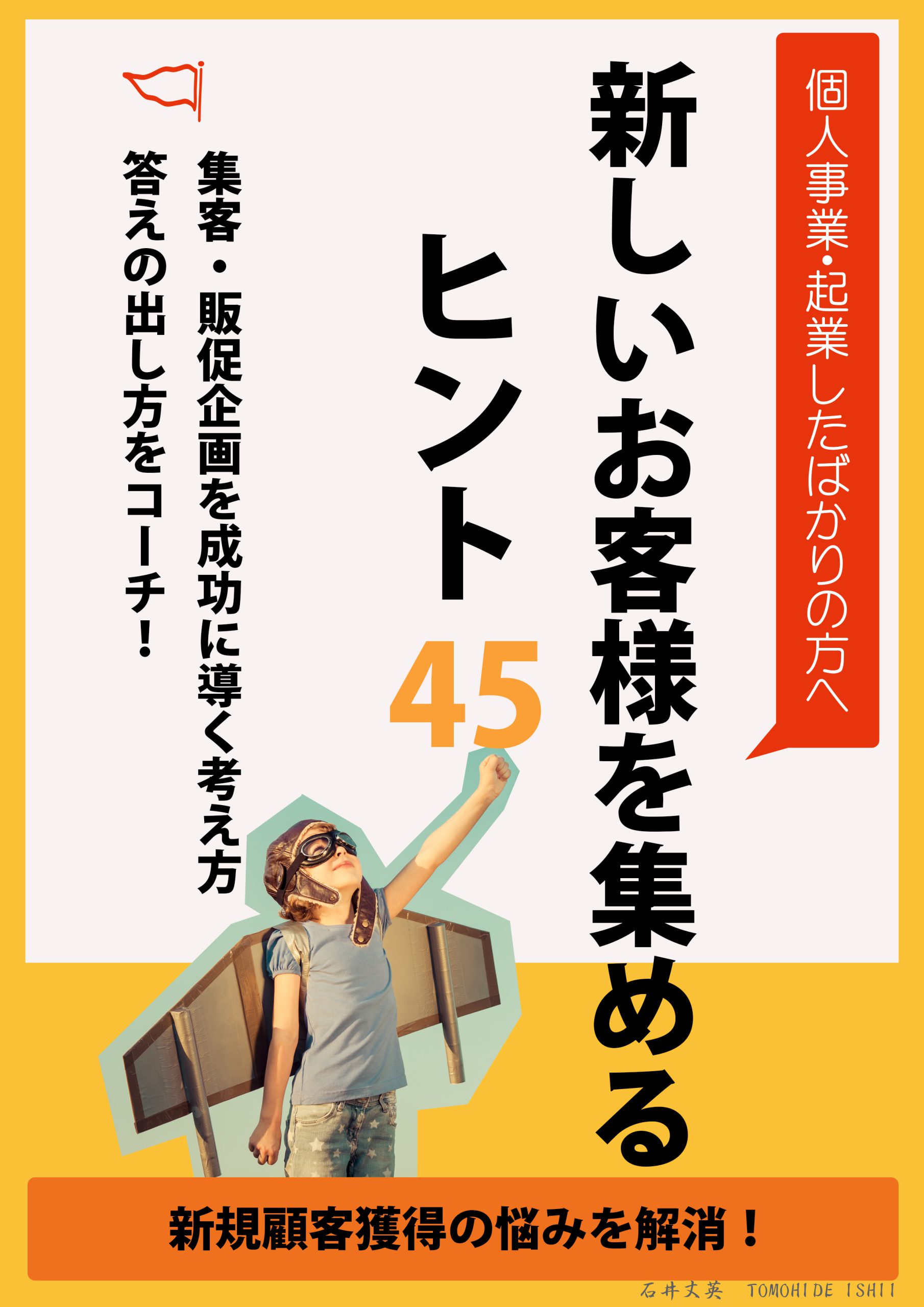「頑張らない営業のヒント」として、過去に「最低でも3か月は継続してみる」と題して、短期的な成果主義ではなく、顧客との信頼関係構築に重きを置いた「頑張らない営業」を提唱しました。
あれから時が流れ、営業を取り巻く環境は劇的に変化しています。
しかし、当時から変わらない本質があります。
それは、「結果を焦らず、質の高い関係性を築くことの重要性」です。
「今すぐ!」の時代から「最適解」を求める時代へ
かつては「スピード」「今すぐ!」「今でしょ」といった言葉が流行し、営業においても即座の成果が求められがちでした。
行動の速さは確かに重要ですが、「すぐに結果が欲しい」という思いは、往々にして営業側の都合を優先する「自己中心」な姿勢につながります。
月末に上司と訪問する営業担当者の顔に、その焦りと恐れが表れるのを見たことがある方もいるかもしれません。
これには「泣き落とし」の意味もあるようでしたが、訪問される側は“いい迷惑”の何物でもないですね!
現代の顧客は、営業担当者の都合で契約を結ぶことは稀です。
本当に顧客の心をつかむには、時間をかけた信頼関係の構築が不可欠であるという事実は、今後も揺るがないでしょう・・・
AIが当たり前になった時代の営業トレンド → テクノロジーと「人間力」の融合
2025年から数年後を見据えると、営業はAIとテクノロジーの進化により、さらなる変革を遂げて行くことは容易に想像できます。
-
AIによるハイパー・パーソナライゼーションと効率化
AIは顧客との交流の大部分を担い、購買履歴、行動パターン、好みなどの膨大なデータを分析することで、個々の顧客に合わせた「超パーソナルな体験」を提供可能にします。これにより、営業担当者は日々のルーティンワークから解放され、より戦略的で創造的な活動に集中できるようになります。
要は、面倒な分析と準備はAIに任せて(活用して)、顧客の心を掴むにはどうするか?という“アナログ思考”を取り入れることもポイントです。 -
営業担当者の役割の変化 → コンサルタントと信頼の架け橋
AIが情報提供や初期対応を効率化する一方で、営業担当者の役割は「製品を売る人」から「顧客の課題を解決するコンサルタント」、そして「信頼できるパートナー」へと進化します。複雑な問題解決、ビジネスケースの構築、組織内の調整、そして何よりも人間的な共感と深い関係性の構築において、人間の営業担当者は不可欠な存在になります。
-
ハイブリッドな顧客接点
オンラインとオフラインの融合が進み、顧客は自身にとって最適なチャネルで企業と接点を持つことを求めます。営業担当者は、AIなどデジタルツールを駆使しつつ、必要に応じて直接対面での深いコミュニケーションを通じて、顧客体験全体を「上手く自動化」する役割を担います。
-
顧客体験全体のデザインと「エンパシー」(顧客が何を考え、どう感じるかを想像する力)
顧客は、単なる製品やサービスだけでなく、購入前、購入中、購入後を通じた一貫したシームレスな体験を期待しています。AIが効率性を高める一方で、顧客の感情や潜在的なニーズを理解し、共感に基づいた対話を通じて深い関係を築く「人間的な触れ合い(ヒューマンタッチ)」の価値は、これまで以上に高まっています。
AIはアイディアやデータをスピーディーに提供してくれる「ツール」
そして、それをどのように顧客に対して使い、満足してもらえるか?を考えるのが、営業マンの役割です。
再び提唱する「最低でも3か月」の継続
このような変化の中でこそ、過去に提唱した「最低でも3か月は継続してみる」という原則が、新たな意味を持ち始めると考えます。
3か月という期間は、AIが生成したパーソナライズされた情報を提供するだけでなく、営業担当者が顧客と本質的な信頼関係を築くために必要な時間の目安となります。
月に1回会うとして3回の面会を重ねることで、単なる顔見知りから、互いに理解し合える関係へと発展させることが可能な期間です。
重要なのは、その面会内容の「質」をいかに高めるかです。
AIが提供するデータや分析を活用し、顧客のビジネスや個人的な課題に深く踏み込み、共感し、共に解決策を考える。
そうすることで、営業担当者は単なるサプライヤーではなく、顧客にとって真に価値あるパートナーと変貌します。
結果がすぐに出なくても、焦る必要はありません。
AIが当たり前になって以降の営業は、短距離走ではなく、AIという強力なサポートを得た長距離走と考えてみましょう!
データとテクノロジーを賢く使いこなしながらも、人間だけが提供できる「信頼」と「共感」を軸に、粘り強く顧客との関係を育むこと。
これこそが、未来の営業で成果を出すための「頑張らない」けれど「深く繋がる」営業スタイルなのです。
AIが当たり前になって以降の時代、この考え方で進んで行きましょう!